
正解のない“遊び”が再生の種になる。ヤマハ発動機×ハーチが「PLAY for REGENERATION」で共に描く未来
- On 2025年11月4日
ヤマハ発動機株式会社(以下、ヤマハ発動機)とCircular Yokohamaを運営するハーチ株式会社(以下、ハーチ)では、ヤマハ発動機 横浜オフィスの共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(リジェラボ)」にて、全6回のイベントシリーズ「PLAY for REGENERATION ―消費する遊びから、再生する遊びへ―」を2025年7月より開催しています。
本シリーズは、”再生”を共通の問いとし、遊びを通じて新たな事業や共創の芽を育てていくことを目的としたプログラムです。「自分自身」や「日々の暮らし」といった内面(Inner)の視点から出発し、社会や環境といった外側(Outer)とのつながりへと視野を広げていきます。その接点にあるモビリティや共創の可能性を遊ぶように探りながら、リジェネラティブ=再生の視点を育んでいくことを目指しています。
なぜ今「再生」というテーマを選び、このイベントシリーズが生まれたのか。そして、何が共鳴し、ヤマハ発動機とハーチによる共創につながったのか。その背景を知っていただきたいという想いを込めて、実際に企画運営を担うメンバーが集い、この取り組みの裏側について語りました。本シリーズのテーマでもある「遊び」の心を込めて、ヤマハ発動機が運営するメディア「RePLAY!」と、ハーチが運営する横浜のサーキュラーエコノミー推進プラットフォーム「Circular Yokohama」の2媒体にわたりお届けします。
話し手
鈴木啓文さん(ヤマハ発動機)

ヤマハ発動機 共創推進グループ。海外での生活経験から、グローバルな環境課題への取り組みに関心を持つ。リジェラボ運営チームのリーダーを務める。
嵩原安宏さん(ヤマハ発動機)

ヤマハ発動機 共創推進グループ。国際交流基金、京都橘大学を経て産官学の職場を循環。海外駐在も含めて経験した多様な価値観をリジェラボ運営に活かし、イベント企画等を担当している。
室井梨那(ハーチ)

横浜市出身、PLAY for REGENERATIONの企画運営を担当。Circular Yokohamaでは地元に根差したネットワークと国際的な視野を活かし、取材やツアー企画、地域の活性化に取り組んでいる。
丸山桃加(ハーチ)

デンマーク・フォルケホイスコーレ留学で心の豊かさを学び、帰国後は社会の循環システムについて研究。恩がめぐる社会づくりを目指し事業に取り組んでいる。PLAY for REGENERATIONでは、ケータリングや運営を担当。
“遊びの余白”が、自由なアイデアを生む
イベントシリーズのタイトル「PLAY for REGENERATION ―消費する遊びから、再生する遊びへ―」、そして開催場所であるリジェラボのコンセプト「地球がよろこぶ、遊びをつくる」でもキーワードとなっている「遊び」。
ヤマハ発動機は長年、多様なモビリティを通じて自然の中における人間の「遊び」の可能性を広げてきました。
Circular Yokohamaでは、サーキュラーエコノミーをより楽しく、より多くの方に親しんでほしいという想いを込めて「Playful Circularity(循環を、あそぼう。)」をテーマに掲げ、横浜市内で生まれた循環型のプロダクトやサービスを集めた移動式ミュージアム「YOKOHAMA CIRCULAR DESIGN MUSEUM」を開催しています。
私たちは、物心ついた頃から自然と遊ぶことに親しんでいますが、そもそも何が「遊び」で何が「遊び」ではないのか、その定義はとても曖昧です。大人になってからの「遊び」とは、いったいどういったものなのでしょうか。

ヤマハ発動機 共創推進グループ 鈴木啓文さん
鈴木さん:“遊び”って何だろうと考えたとき、一番本質にあるのは“自発的で主体的なもの”だと思います。誰かに強制されるものではなく、自分が「楽しい」「やってみたい」と思うからこそ生まれるものですよね。
ヤマハ発動機はもともと、バイクやボートといった製品が代表であるように、遊びに対する情熱が高い人たちが集まっている会社です。リジェネラティブ(再生)の取り組みも、義務ではなく、「楽しいからやろう」という気持ちを大切にしています。結果的にその想いが循環して、良い形で社会に還元されていくのが一番良い。そんな考え方が「PLAY for REGENERATION」というテーマにつながっています。
室井:“遊び”という前提があると、寛容になれますよね。正解や失敗がなく、誰かと比べる必要もない。だからこそ、純粋に思考を広げて「おもしろい」という直感を大切にできると思うんです。
私は大学で学校教育について学んでいたのですが、日本の教育は欧米と比較して、正しい答えを求めがちな傾向にあると考えていました。一方、このシリーズの場では”正解がないこと”が前提です。誰かに評価されるためではなく、「おもしろそう」「一緒にやってみたい」というポジティブな気持ちから発想が広がっていく。そうした遊びの余白こそが、自由なアイデアを生む土壌になっていると思います。

効率や成果の外側にある”遊び”の価値
丸山:私はミーティングのときから、すでに”遊び”の感覚があります。普通なら業務的なフィードバックの場になると思うのですが、このプロジェクトの企画会議では「それ、おもしろいですね」と盛り上がって、自然とアイデアが広がっていくんです。仕事の会議というより、お互いがワクワクするものを共有するブレインストーミングに近くて、次はどんな議論になるんだろう?と毎回楽しみにしています。
嵩原さん:ハーチさんは、もともとメディア事業を通じてよりよい社会の実現に取り組んでいる会社ですよね。日々そうしたことを考えながら日々活動しているからこそ、さまざまな引き出しがあって、私たちにはない発想をたくさんもらえています。
たとえば、Vol.2の『都市の”体温”の再生』をテーマにしたイベントでは、横浜市建築局のアップサイクルプロジェクトであるREYO(※)とコラボレーションして、体育館の床材を使った「一見役に立たないけど、都市の体温を上げる道具」を考えるワークショップを行いました。新規事業の部門にいると、どうしても「利益をあげるもの、社会に役立つものを考えなければ」という発想になりがちなんです(笑)。だからこそ、ハーチさんが「無駄づくり発明家」のアイデアを提案してくれたときは、普段とは違う頭の使い方ができそうだと思って、ぜひやりたいと思いました。
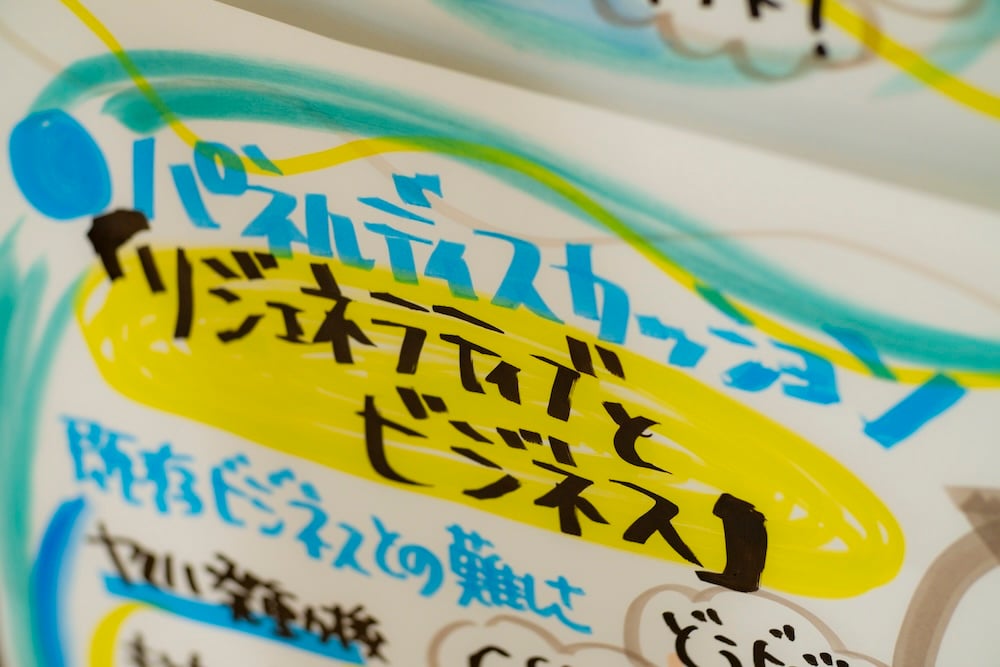
リジェラボで過去に開催されたイベントのグラフィックレコーディング
丸山:「冒険的だけど、おもしろそうだから入れてみよう」と思って私たちが提案したものが、意外と採用されることが多いんです。ワークショップの内容を決めたときも「無駄なものをつくるの、いいじゃないですか!」と大賛成してもらえて、嬉しかったですね。
嵩原さん:世の中では、効率的であることや短期で成果を出すことが価値とされがちですが、あえてその逆を行って自発的に考えるからこそ見えてくるものがあります。リジェラボというスペースを使って「無駄なものを考えよう」と堂々と言えるのは、”遊び”を軸としてきた私たちの強みです。利益や合理性だけでは生まれない、感性を重視したアイデアを一緒に育てていけることが、この共創の一番の価値だと感じています。
※「REYO(リヨー) 横浜市再利用材プロジェクト」は、横浜市建築局による、公共建築物の古材を新たな価値へとアップサイクルする取り組みです。市内外の民間事業者と連携しながら、公共建築物から生じる廃材の循環を促し、サーキュラーエコノミーを推進しています。

ヤマハ発動機 共創推進グループ 嵩原安宏さん
違う土地で、違う事業に取り組んできた二社だからこそ見えること
「PLAY for REGENERATION 」では、これまでに3回のイベントを開催(本記事公開時点)。Vol.1では「たくさんの『再生』が集まったとき、社会はどう変わるのだろうか?」、Vol.2では「わたしたちの創造力は、都市の『体温』を再生できるか?」、Vol.3では「『それ、儲かるの?』を超えるには。大企業・地域の実践者に学ぶ大地を再生する事業のリアル」という問いを掲げ、登壇者や参加者とともに対話を重ねてきました。
“リジェネラティブ”という、まだ十分に言語化されていないテーマをさまざまな角度から探究するこのイベントシリーズ。一見、冒険的にも思える取り組みを、なぜあえてシリーズで開催しようと考えたのでしょうか。
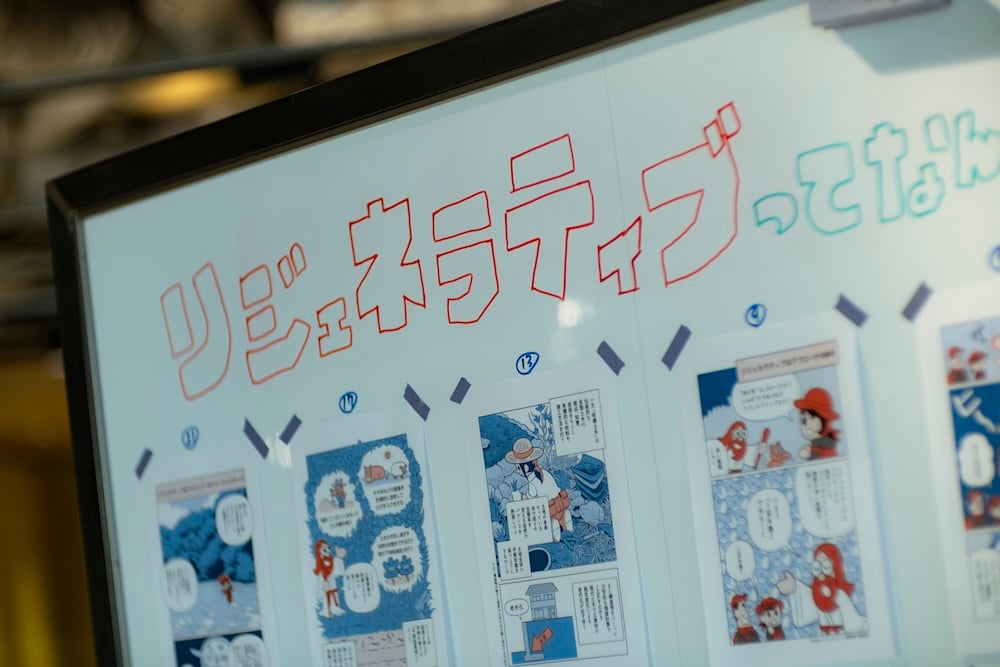
リジェラボでは、オリジナル漫画「リジェネラティブってなんだろう?」を展示
鈴木さん:企画の段階で、「リジェネラティブな取り組みを広め、その認知度を高める」というゴールを設定していました。ただ、それを単発のイベントで実現するのは難しいですよね。そこでハーチさんと一緒にシリーズ化し、共創の種を育てていけないかと考えたんです。
室井:最初にお話をいただいたとき、私たち自身も「リジェネラティブ(再生)って何だろう?」と改めて考えさせられました。“持続可能”や“循環”とはどう違うのか。なぜヤマハ発動機さんは“サステナブル”ではなく“リジェネラティブ”に取り組むのか。そんな問いから、この企画は始まったように思います。
鈴木さん:ハーチさんと知り合うまでは、まさか横浜で養蜂やコンブの養殖が行われているなんて想像もしていませんでした。都市の中でそうした取り組みをしている人たちとどうつながり、知見を共有していけるか。そこが重要なポイントだと思うんです。まだ存在していない関係性を生み出していくことこそ、都市に拠点を置く企業として考えるべきテーマだと思います。
嵩原さん:私たちの部署は「ものづくりにこだわらない新規事業」を考えるチームで、社会課題にオープンに挑む“共創”を前提にしています。新しく拠点を構えたばかりの横浜で仲間を集めるのは大きな挑戦でしたが、シリーズを重ねるうちに常連の方や「近くなので寄ってみた」という方も増えてきました。横浜でつながりを持つハーチさんと組むことで、地域との新しい接点が生まれているように感じます。

Circular Yokohama編集部 室井
室井:そう言っていただけると嬉しいですね。私たちはこれまで“横浜”という軸を意識して活動してきたのですが、今回ご一緒したことで、いい意味でその枠を超えて考えられるようになった気がします。”リジェネラティブ”というテーマがあれば、静岡でも東京でも、地域を超えてつながっていける。実際にイベントを通して新しい出会いが生まれ、私たち自身にも新たな可能性が広がっています。
鈴木さん:ローカルメディアならではの深さと、大企業のネームバリューが組み合わさることで、これまでにないグラデーションのある参加者層が生まれたようにも感じています。初回から、確かな手応えがありました。
「始めてみたい」という気持ちが生まれることが一番嬉しい
嵩原さん:私たちが“リジェネラティブ”や“遊び”をテーマにしているのは、経済的な効率を追い求めるためではなく、もう少し違う時間軸や価値観で物事を見つめ直してみよう、という提案なんです。
Vol.1では、「リペア」をテーマにしたゲストトークや、ハーチさんが制作した映画「リペアカフェ」の上映会を行いました。壊れたものを直すより、新しく買うほうが早くて合理的かもしれません。それでも“直して使う”というテーマを選んだのは、ものづくり企業として環境との関わりを見つめ直し、作ったあとのことにも目を向けたいという想いがあったからです。
丸山:サステナビリティが企業ブランディングの一環として語られることも多いなか、ヤマハ発動機さんは、自分たちがこれまでに生み出してきた「消費」の事実から目をそらさず、新しい価値観を育てようとしていますよね。さらにそこに“遊び”を掛け合わせているのが本当にかっこいいなと思います。

Circular Yokohama編集部 丸山
嵩原さん:廃棄物を見せることは、企業としては勇気のいることです。それでも、あえてさらけ出して一緒に考えることで新しい価値が生まれるかもしれない。必ずしもそれが経済的でなくても、別の形の価値があるはずです。アンケートに「自分も小さなことから始めてみようと思いました」と書いてくれた方がいて、それがとても印象に残っています。このイベントが、誰かの動き出すきっかけになれたら嬉しいですね。
室井:リジェラボのように、本質的なサステナビリティを追求して設計された場所でイベントを開けるというのは、本当に貴重ですよね。テーマだけではなく、会場の什器や運営のあり方まで含めて再生的に考えられる環境はまだまだ少ないと思います。だからこそ、ここで活動できること自体が大きな励みになりますし、伝える立場としても自信が持てます。
嵩原さん:私たちが今いるデスクも、弊社製のプールの底板を使って作ったものです。バイクやボートもそうですが、「自分たちが楽しい」「本当にいい」と思えないと、本気になるのは難しいですよね。実は「遊び」というテーマは、社内でかなり議論を重ねて決めたものなんです。「環境のために」と真面目に呼びかけるだけでは、なかなか社会のうねりは生まれない。だったらみんなが共感できる形で遊びに変えてやろう、と考えました。

インタビューはリジェラボを象徴する、ヤマハ発動機製プール底板を使用したデスクで実施
丸山:たしかに、いつも真面目にまっすぐ生きるのは難しいなと感じることがあります(笑)。自分たちにないものを求めるのではなく、あるものを強みにするという形が主流になるといいですよね。
嵩原さん:正解を求められる社会に、疲れてしまうときもあるはず。だからこそ、こうした”正解のない場所”に存在意義が生まれる時代なのかなと思います。自宅と職場に続くサードプレイスのような、少し立ち止まって考えられる場所になれたら嬉しいです。
新しいからこそ柔軟になれる。横浜発の”再生”の連鎖を目指して
嵩原さん:横浜は、人や企業、行政のつながりがとても強い地域ですよね。行政が中心となって企業や団体を巻き込む動きも盛んで、共創の文化がしっかりと根づいているように感じます。私たちも今年(2025年)の春に、横浜未来機構と横浜市経済局が開催する都市型フェス「YOXO FESTIVAL」に出展しましたが、あれだけの規模のイベントを市内の複数拠点で開催できるのは、横浜ならではだと思います。
室井:循環や共創といったテーマが、そうした動きを生み出しているのかもしれません。横浜は大きい自治体なので、何かを変える難しさもあると思いますが、“循環”のような新しい分野だからこそ柔軟に受け入れてもらえる余地がある。そうした環境が横浜にはあると思いますし、リジェラボのような共創拠点がそれを後押ししていると感じます。

嵩原さん:最近では、「リジェラボを使って自分でもイベントをやってみたい」という声をいただくことが増えました。私たちだけで完結するのではなく、ここから新しい活動が広がっていくのが理想です。誰かの「やってみたい」が、また次の”再生”を生む。そんな連鎖を大切にしていきたいです。
室井:このシリーズで出会った方々が横浜のネットワークに加わってくださったり、別のプロジェクトでご一緒したり、そうした偶発的な出会いこそが”再生”の原動力になると思っています。横浜には、挑戦したい人が集まれる土壌があると思うんです。せっかくなら横浜でやってみたい、関わりたいと思ってくれる人たちを巻き込みながら、さまざまな場所で共創が生まれていったらいいですよね。そうした動きが結果的に社会全体の再生につながっていくと思うので、これからも横浜から広がる新しい循環をつくっていきたいと思います。

編集後記
“遊び”という言葉の中には、自由さと創造性、そして寛容さが息づいています。立場を越えてつながった人々が、それぞれの「やりたい」という気持ちから動き出すとき、きっと新しい未来のかたちが見えてくるはずです。“遊びながら再生する”という新しい挑戦は、これからどんな広がりを見せていくのでしょうか。
本イベントシリーズは、今後も続いていきます。次回の「PLAY for REGENERATION」のイベント詳細については、Circular Yokohamaまたはリジェラボの公式サイトをご確認ください。
なお、ヤマハ発動機が運営するメディア「RePLAY!」では、イベントシリーズ「PLAY for REGENERATION」がどのような経緯で始まり、ハーチとの共創に至ったかを紹介する記事が公開されています。本記事とあわせて、ぜひお楽しみください。
Circular Yokohamaでは今後も、サーキュラーエコノミーを推進する協働・共創の取り組みを続けてまいります。
【関連サイト】RePLAY!
【関連サイト】リジェラボ(横浜共創スペース)
【関連記事】【11/17】ヤマハ発動機、「海の再生をビジネスで広げる」をテーマにしたトークイベントを横浜で開催
【関連記事】【9/30】ヤマハ発動機、「大地を再生する事業のリアル」に迫るトークイベントを開催
【関連記事】【9/3】ヤマハ発動機、”再生”をテーマにしたイベントシリーズの第二回「わたしたちの創造力は、都市の『体温』を再生できるか?」を開催
【関連記事】【7/29】ヤマハ発動機、”再生”をテーマにしたイベントシリーズ「PLAY for REGENERATION ―消費する遊びから、再生する遊びへ―」を開始
金田 悠
最新記事 by 金田 悠 (全て見る)
- 済生会横浜市東部病院に就労支援事業所と提携した「SDGsロッカー」が設置 - 2026年1月21日
- レコテック、横浜市1,200拠点の廃棄物管理DXに向けて資源循環プラットフォーム「pool」試験導入を開始 - 2025年12月15日
- ファンケル、横浜市に累計25,000個超のアップサイクル植木鉢を寄贈したと発表 - 2025年12月8日








