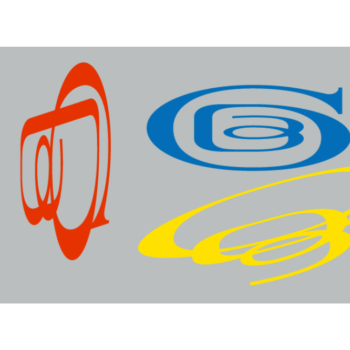廃棄物処理を憧れの仕事へ。横浜環境保全が「想造」する、新しいカタチのやさしさ
- On 2025年9月12日
横浜市金沢区に拠点を置く横浜環境保全株式会社(以下、横浜環境保全)は、1972年の設立以来、半世紀以上にわたり横浜の環境インフラを支えてきました。
社会に必要とされながらも、しばしば地味で大変な仕事と思われがちな廃棄物処理業界の常識を覆すべく、ごみ収集車を子どもたちの憧れの存在へと変え、業界全体の価値向上を目指す同社。その取り組みは、「未来、そして子どもたちのために」という揺るぎないビジョンから生まれています。
この記事では、代表取締役社長の髙橋義和氏と金沢事業所所長の濱俊介氏へのインタビューを通じて、同社が描くビジョンを紐解き、廃棄物処理業界のイメージを根底から変え、循環型社会へと導く挑戦の軌跡を追います。
横浜の循環を支える、横浜環境保全の事業と多様性
横浜環境保全は、横浜市から第一号で一般廃棄物処理の許可を得て以来、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬から、自社工場での中間処理・リサイクルまでを一貫して手がけています。

横浜環境保全株式会社・金沢事業所
同社の事業は多岐にわたり、オフィスや商業施設から出るビニール・プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず、金属くずなどの産業廃棄物から、飲食店やスーパーマーケットから出る生ごみまで、あらゆる事業活動に伴う廃棄物を扱っています。これらの廃棄物は、再資源化や堆肥化のプロセスを経て、再び社会で活用されます。

横浜環境保全の中間処理場(破砕・圧縮・溶解)の様子
特に、事業系一般廃棄物の収集においては、横浜市全体の月間約2万トンという排出量に対し、同社が大きな割合を担っています。約190台に及ぶ車両が市内全域を巡回し、その広範なネットワークと処理能力で、横浜のまちの清潔さを守る重要な役割を果たしています。

横浜市内の商業施設から回収したペットボトル資源をベール化する様子
無骨なごみ収集車を「みんなが誇れる働く車」へ
廃棄物処理業界の「顔」とも言える、ごみ収集車(パッカー車)。しかし、代表取締役である髙橋氏が事業を引き継いだ2011年当時、ごみ収集車は社会から注目される存在ではありませんでした。そこで髙橋氏が考えたのが、ごみ収集車を「デザインパッカー車」として生まれ変わらせることでした。

代表取締役社長・髙橋義和氏
髙橋氏「ある時調べてみたら、子どもたちに人気の『働く車ランキング』でごみ収集車が3位にランクインしていたんです。しかし、現実のごみ収集車はボコボコで汚い車ばかり。そこで、子どもたちが笑顔になれるような、カラフルでポップなデザインの車を作ろうと思ったのです」
そうして、社員から車体のデザインを公募することから始まったこの取り組み。今や地元の小学校と連携し、子どもたちが描いた絵を車体にプリントするコンテストも開催するようになりました。

本牧南小学校の児童がデザインしたパッカー車
髙橋氏「デザインパッカー車は、横浜環境保全を『社会と子どもたちに誇れる会社にする』という私たちの経営理念を突き詰めていった結果、たどり着いた答えでした。未来を担う子どもたちに、この仕事に興味を持ってもらい、『将来はあの車に乗って仕事がしてみたい』と言ってもらえるような業界にしたいのです」
この取り組みは、社員の家族にも大きな変化をもたらしました。
以前は「ごみ屋さん」という言葉の響きに、複雑な想いを抱く社員の家族もいたそう。今では「家族は環境の仕事をしています」と誇らしげに語るようになったといいます。デザインパッカー車は、働く人々の誇りを高め、社会からの認識を変えるための強力なツールとなっています。

横浜環境保全の考え方が導く、社員の幸せと業界の未来
そんな髙橋氏が大切にしているのが、社員と彼らを支える家族の幸せです。
例えば、汚れた作業着を家で洗う家族の負担を減らすため、すぐに乾く素材の制服を用意し、社内にも洗濯機を設置しました。さらに、現場で働く社員のために、消耗品である作業用の靴下も定期的に支給しています。
これらの施策の根底にある考え方は、髙橋氏が経営学を学ぶ中で出会った京セラフィロソフィ。それをベースに、独自に作り上げた「横浜環境保全の考え方」です。この哲学は、社員一人ひとりの人間性を高め、働くことへの意義を見出すことを目的に、全社員で共有されています。
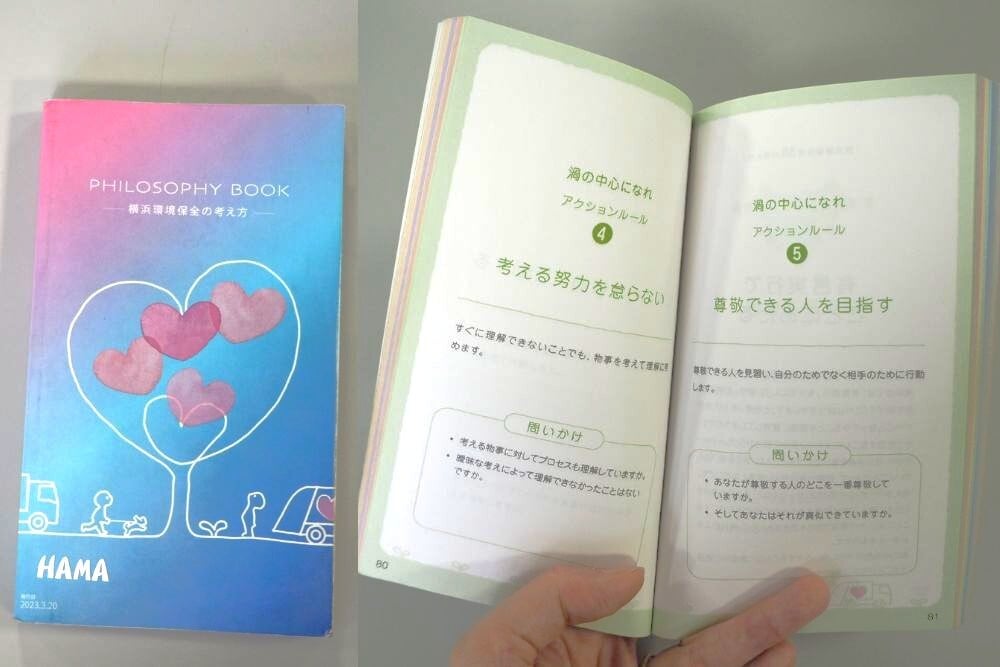
独自の企業哲学「横浜環境保全の考え方」を伝えるハンドブック
髙橋氏「仕事を通して人間性を高めることが、私の考える働くことの目的です。働くこと自体に目的や意義を持ってほしい。そうすれば、精神的にも物質的にも豊かな人生を送ることができる。社員が幸せになれば、自然と会社もよくなり、それが社会への貢献につながっていくと信じています」
慣れない取り組みに、当初は社員からの反発もあったといいます。しかし、朝礼や会議の場面での唱和など、継続的な社内浸透に取り組む中で、社員の意識が少しずつ変化し、社内の雰囲気も改善されていきました。
高橋氏とともに、この取り組みを伴走してきた所長の濱氏は次のように話します。
濱氏「以前より、従業員が楽しそうに働くようになりました。加えて、近隣住民との関係性にも変化がありました。昔はごみ収集に関するクレームばかりだったのが、最近では幼稚園からも感謝の手紙が届くようになりました。そのような外部からの反応も後押しとなって、企業理念がいかに大事なものか実感することができています」
企業理念の浸透によって、従業員自らが事業に関わる意味や仕事の目的を考えるようになる。そして、そういった従業員の変化が地域住民にも伝わり、より良い地域づくりの一端を担っているのかもしれません。

金沢事業所所長・濱俊介氏
ごみ問題解決のその先へ。次世代に託す壮大なビジョン
横浜環境保全は、資源のリサイクルにも独自のアプローチで取り組んでいます。
例えば、飲食店から出る生ごみを回収し、それを微生物の力で自然発酵させて、「ハマのありが堆肥」として生まれ変わらせています。この堆肥は、神奈川県から「かながわリサイクル製品」として認定を受けており、農家や農園で活用されています。

堆肥化の様子
さらに同社は、廃プラスチックやその他のあらゆる可燃性廃棄物を破砕圧縮し、ガス発生室内で乾溜してガス化し、一部を発電するリサイクル施設の建設を計画しています。これは、ビニール系廃棄物の焼却処理による環境負荷を減らし、化石燃料の代替品として活用することで、資源の循環をより高度なレベルで実現しようという画期的な試みです。
髙橋氏「私たちは、廃棄物処理を単なるビジネスではなく、地球規模の課題解決と捉えています。私たちの代が挑戦できるのは、地球規模の課題にとどまるかもしれません。けれど、次の世代には『宇宙のごみまでリサイクルするような会社を目指してほしい』と伝えています。今はまだ絵に描いた餅かもしれませんが、この壮大なビジョンこそが、私たちの原動力です」

市内イベントにおけるパレードの様子(出典:横浜環境保全Facebookページ)
横浜環境保全では、「みらいプロジェクト ~ 夢をカタチに 2030 ~」を打ち出し、2030年ミッションとして、次のように宣言しています。
新しいカタチの「やさしさ」を想造し「企業価値」を高めます。
ひとりひとりの思いを紡ぎ笑顔あふれる企業にします。
地域の子どもたちがごみ収集車に手を振ってくれるように、これからも新しいカタチのやさしさを「想造」すべく歩みを進める横浜環境保全。ごみ問題の解決から循環型社会の実現へ。そしてその先の「地球健康貢献企業」という壮大なビジョンに向けて、これからもその取り組みは続きます。

編集後記
今回の取材は、ビジネスの成功が売上や規模だけでは測れないことを改めて教えてくれました。
収益や数字は重要な指標ですが、それ以上に大切なのは、その活動を通じて「誰を幸せにできているか」「社会にどんな意味を生み出しているか」ということ。これは、持続可能な社会づくりが求められる今、企業にとって欠かせない視点とも言えます。
また、横浜環境保全は、企業理念を通して従業員に対して働く意義や人生の目的を見出すきっかけを生み出しています。そして、この従業員の前向きな気持ちが、地域住民に与える「廃棄物業界」への印象を変えているのかもしれません。
取材の中で、髙橋さんは「応募したデザインがパッカー車に採用された子どもが、大きくなって横浜環境保全に就職してくれたんです」というほほえましいエピソードも教えてくださいました。企業理念を出発点に、従業員や地域住民、そして未来を担う子どもたちへと広がる、同社の社会的価値の大きさに気づかされます。
従業員の笑顔、家族の誇り、そして子どもたちの未来。横浜環境保全が追求する「新しいカタチのやさしさ」は、同社らしい持続可能な社会の実現に不可欠な要素です。
Circular Yokohamaでは、これからも横浜環境保全の挑戦を追い続けます。
【関連記事】廃棄物から価値を生む。リサイクルで横浜の資源循環を支える「グーン」
【関連記事】資源と想いが循環するまちへ。春秋商事に学ぶ、地域共生とリサイクルのかたち
【関連記事】リサイクルをミラクルに。J&T環境に学ぶプラスチック循環の最前線
【参照サイト】横浜環境保全
【参照サイト】環境用語集:「乾留ガス化」| EICネット
【参照記事】一般廃棄物処理業者名簿 横浜市
Momoka Maruyama
最新記事 by Momoka Maruyama (全て見る)
- 廃棄物処理を憧れの仕事へ。横浜環境保全が「想造」する、新しいカタチのやさしさ - 2025年9月12日
- 横浜市資源循環推進プラットフォーム始動、動静脈連携で描く循環型社会の未来 - 2024年12月26日
- 「木の実のクラフト〜ハーブティーを楽しみながら、 自分だけのミニガーデンを作ろう〜」を開催しました【イベントレポート】 - 2024年11月28日