
横浜市資源循環推進プラットフォーム始動、動静脈連携で描く循環型社会の未来
- On 2024年12月26日
2024年11月27日、「横浜市資源循環推進プラットフォーム」キックオフイベントが市内のVlag Yokohamaで開催されました。このイベントでは、横浜市、環境省、経済産業省、横浜市の動静脈企業が集い、脱炭素社会の実現と循環型経済の推進に向けた意欲的な議論が展開されました。行政と民間企業が連携し、循環型社会を構築する新たなステージがスタートしました。
試行錯誤を乗り越えた、新たな挑戦
横浜市資源循環局長の金髙隆一氏が開会挨拶で述べたのは、資源循環推進の重要性と新たな試みへの期待です。「概念としては理解されている循環経済ですが、具体的な取り組みとして実現するには多くの課題があります。試行錯誤を重ねながら、それぞれの現場での取り組みが進むことを期待しています」と話しました。

横浜市資源循環局長の金髙隆一氏
第1部「プラットフォームが目指す姿」
第1部では、「プラットフォームが目指す姿」をテーマに、横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課担当課長の大島貴至氏と株式会社グーン代表取締役の藤枝慎治氏のクロストークが行われました。

まず大島氏は、廃棄物の有価物化やリサイクルの推進には法規制やコストの壁があることを指摘しました。「リサイクルには費用がかかるため、適正処理が必ずしもリサイクルに繋がらないジレンマがあります」と述べ、環境施策が抱える課題を説明しました。
また、大島氏は「市の指導による適正処理だけでは限界がある」と続けて強調します。動脈産業と静脈産業の連携を深めることで、コスト面の課題を克服し、資源循環のモデル都市を目指す考えを示しました。

横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課担当課長の大島貴至氏
次に藤枝氏は、「廃棄物処理業者から資源生産者への役割の変化が求められています。経済と環境を両立する新たなグランドデザインが必要です」と語り、横浜市のプラットフォームがそれを実現する場になるとの期待を示しました。
藤枝氏はさらに、「自治体と企業が共創するフロントラインが横浜市にあります。このプラットフォームをきっかけに、循環型経済を牽引するモデルをつくりたいと考えています」と意欲を語りました。

株式会社グーン代表取締役の藤枝慎治氏
第2部「循環型社会への具体的アプローチ」
第2部では、資源循環に携わる動静脈企業が登壇し、事業の紹介やプラットフォームでの展開を期待する取り組みについて話ました。
ZACROS株式会社「製品設計とリサイクルの両立」
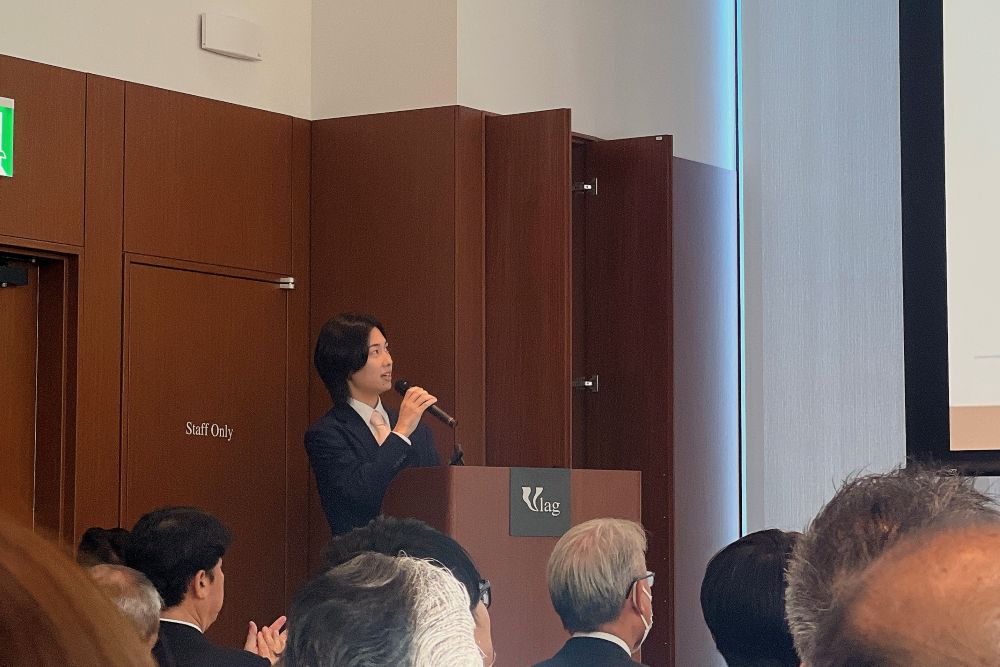
ZACROS株式会社の竹田和馬氏
ZACROS株式会社は、環境負荷低減を目指し、廃棄物削減とケミカルリサイクルに注力しています。同社は、「複雑な構造を持つプラスチックのリサイクルは依然として課題が多い。しかし、単一素材化や新たな分別技術の導入を進めることで実現可能です」と述べ、技術革新の方向性を示しました。
さらに、「横浜市との連携で、地域特性を活かした資源循環モデルを確立し、他都市への展開を目指します」と、地域貢献の意義を強調しました。
J&T環境株式会社「プラスチックマテリアルと食品リサイクルのサーキュラー化を目指した仕組みづくり」

J&T環境株式会社代表取締役の長谷場洋之氏
J&T環境株式会社は、「排出・製造側の自治体、企業とリサイクラー/リサイクル品利用者とを結ぶ結節点になることを目指しプラスチックリサイクルや食品リサイクルの仕組みづくりに取り組み、経済と環境の両立を目指しています」と述べました。また、課題点として、技術革新と密接な動静脈連携の必要性を強調しました。
レコテック株式会社「データ活用の未来」

レコテック株式会社代表取締役の野崎衛氏
レコテック株式会社は、データの「見える化」を軸に効率的な資源循環を推進しています。野崎氏は、「データプラットフォームの標準化を進め、国や自治体との連携を深めることで効率性を高める」と説明し、資源循環のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が社会全体の効率性を向上させると述べました。
第3部「環境と経済の両立に向けた挑戦」
第3部では、6名が登壇しパネルディスカッションが行われました。
- 経済産業省 GXグループ 資源循環経済課長 田中将吾氏
- 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課長 松田尚之氏
- 株式会社グーン 代表取締役 藤枝慎治氏
- J&T環境株式会社 代表取締役 長谷場洋之氏
- レコテック株式会社 代表取締役 野崎衛氏
- ZACROS株式会社 横浜事業所 次長 萱野悦二氏

経済産業省の田中氏は、「資源循環は、資源制約、環境制約、そして成長機会を解決する鍵です」と述べ、政策支援とデータ活用の重要性を強調しました。一方、環境省の松田氏は、「地域課題を吸収するには市町村と民間事業者の連携が不可欠です」とし、国の認定制度を活用した効率化に期待を寄せました。

経済産業省GXグループ資源循環経済課長の田中将吾氏
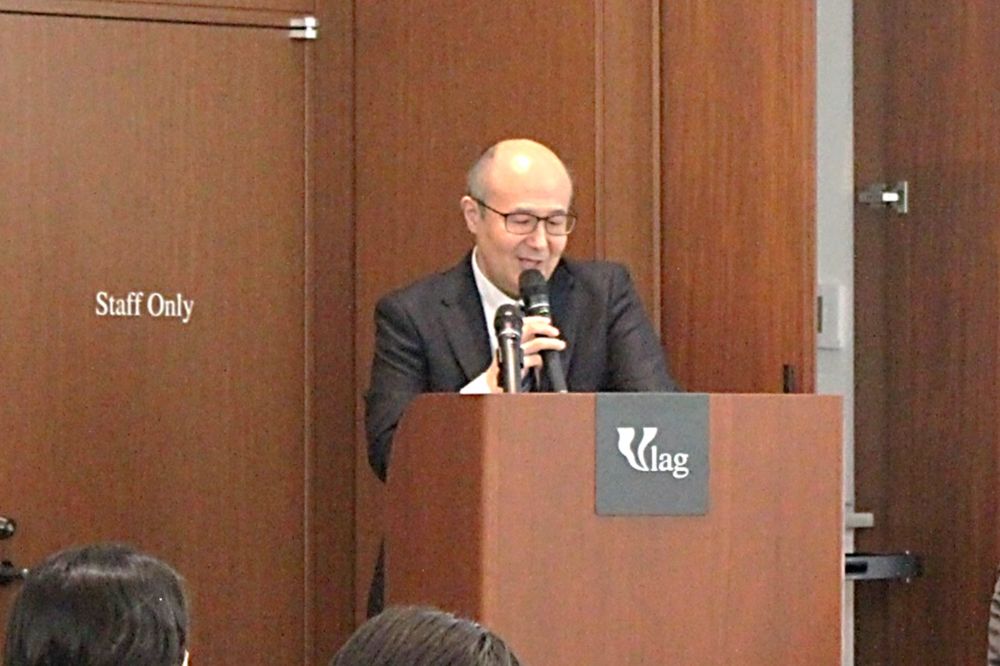
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長の松田尚之氏
株式会社グーンの藤枝氏は「ペットボトルリサイクルは進んでいるが、他のプラスチックリサイクルには技術とコストの課題が多い」と指摘。これに対し、田中氏は「市場形成と技術革新が重要で、ペットボトルリサイクルの成功例を他分野に応用すべきだ」と述べ、ロードマップの作成と技術の可視化を提案しました。
J&T環境株式会社の長谷場氏は「静脈産業のコスト負担が重い現状をどう解決するかが課題」とし、効率的な資源循環モデルの構築を提案しました。一方でレコテック株式会社野崎氏は、「公共調達や法律の枠組みが循環型社会形成の鍵となります」と述べ、規制と市場のバランスの重要性を強調しました。
パネルディスカッションの後半には、経済産業省の田中氏が「データが乱立して繋がらないと意味がない。データプラットフォーム同士を連携させ、ビッグデータとして統合する取り組みを進めています」と今後の展開についても述べました。
閉会挨拶「地域との連携で進む未来」
株式会社春秋商事代表取締役の甲斐陸二郎氏が閉会挨拶を務めました。
甲斐氏は、「本イベントは、横浜市の資源循環における記念すべき第一歩です」と述べました。さらに、「資源循環事業は企業単体では難しく、プラットフォームという枠組みが、連携と効率化を実現する重要な基盤になる」と強調しました。

株式会社春秋商事代表取締役の甲斐陸二郎氏
また、地域と企業が協力することで、これまで実現が困難だった課題が解決できると述べ、「私たちは地域の一員として、皆様の協力を得ながら資源循環を推進していきたいと思います」と締めくくりました。
取材後記
「横浜市資源循環推進プラットフォーム」は、脱炭素社会の実現に向けた動静脈連携の拠点として、全国のモデルケースとなる可能性を秘めています。本イベントを通じて、企業と自治体の協働が資源循環型社会の実現においていかに重要であるかが示されました。これからの取り組みが、地域経済や社会全体にどのような変化をもたらすのか注目が集まります。
【参考記事】横浜市「横浜市資源循環推進プラットフォーム」キックオフイベント開催案内
【関連記事】【11/27】横浜市、「横浜市資源循環推進プラットフォーム」キックオフイベントを開催
【関連記事】食品ロスとプラスチック削減に立ち向かう、横浜市資源循環局
Momoka Maruyama
最新記事 by Momoka Maruyama (全て見る)
- 横浜市資源循環推進プラットフォーム始動、動静脈連携で描く循環型社会の未来 - 2024年12月26日
- 「木の実のクラフト〜ハーブティーを楽しみながら、 自分だけのミニガーデンを作ろう〜」を開催しました【イベントレポート】 - 2024年11月28日
- TBS系SDGsキャンペーン連動プロジェクト「地球を笑顔にする広場2024春」にて、循環をテーマにワークショップを行いました【イベントレポート】 - 2024年8月14日







