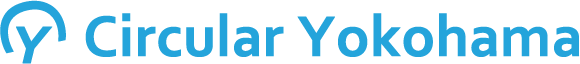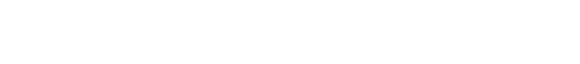【特別対談・前編】横浜の「サーキュラーエコノミーplus」が描く、持続可能な都市の未来
- On 2020年10月24日
2050年には世界人口の約7割が都市部に暮らすと予測されているなか、都市をどのように持続可能な循環型のモデルに移行していくかが世界中で課題になっています。2020年4月に世界で初めて「ドーナツ経済」のモデルを都市政策に採用することを公表したオランダの首都アムステルダムをはじめ、ロンドンやヘルシンキなど、サーキュラーシティ(循環型都市)をビジョンに掲げる都市は数多くあります。
そんな中、横浜市では日本国内のサーキュラーエコノミーを牽引すべく、地域をあげてサーキュラーエコノミーに取り組んでいます。横浜市は日本国内最大規模の政令指定都市であり、これまで人口は増加の一途を辿ってきました。そんな、あまたの「人」が作り上げてきたまち横浜は、サーキュラーエコノミー推進の主軸に「サーキュラーエコノミーplus」を掲げています。
この「plus」は、サーキュラーエコノミーにおける従来の「Planet(環境)」や「Profit(経済)」といった視点だけではなく、「People(人)」の視点をプラスすることを意味しています。そして、サーキュラーエコノミーplusには、ローカル・フォー・ローカル、サステナブルデベロップメント、パラレルキャリア、ヘルスプロモーションの4つの領域があり、公民連携・イノベーションによってその4領域全てを横断的に実現するというモデルになっています。
Circular Yokohamaでは、2020年9月某日、この「サーキュラーエコノミーplus」のビジョンを策定した横浜市政策局共創推進課の関口昌幸さんと、Circular Yokohama編集部の加藤佑による対談を実施し、横浜におけるサーキュラーエコノミー推進の背景や、それに取り組む関口さんの思い、そして今後のビジョンを伺いました。本記事では三部構成となる対談の前編をお届けします。
横浜市政策局 共創推進室 共創推進課、関口昌幸(せきぐち・よしゆき)さん
多様なまち、横浜
関口氏:現在横浜市は市内各地にあるリビングラボを通じてサーキュラーエコノミーを実現していこうと取り組んでいます。そのためにまず必要となるのが、横浜が地域としてどのような課題を抱えているのかを正しく把握することです。
ただ世界でサーキュラーエコノミーが流行っているからという理由で取り組み始めるのではなく、横浜市民の生活にどんな課題があるのかを理解し、それらを解決して横浜をよりよい街にする手段としてサーキュラーエコノミーを推進することが重要です。大事なのは横浜という都市の姿にあった課題解決をすることなのです。
横浜は375万人を抱える日本最大の人口規模を誇る政令市です。それにも関わらず都市としての歴史ははなはだ浅く、本格的に市街地が形成され始めたのは幕末に横浜港が開港してからで、まだ160年ぐらいしか経っていません。
しかも地形が複雑で起伏に富んでいて、平地が少なくて坂も多く、本来ならば人が集住し、交通・交流することで産業経済を興すにはとても不向きな地形をしています。
それが、約160年で375万という基礎自治体として日本一の人口規模を誇る大都市になりました。それは、なぜなのか?未来に対する横浜の持続可能性を考えるうえで、この問いについて答えておくことは、極めて重要なことだと思います。
「横浜」というとテレビや雑誌で必ず紹介されるのは「みなとみらい」や「中華街」などの臨海都心部ですが、これらのエリアは市域の面積割合でみればほんの数パーセントに過ぎず、臨海都心部だけで横浜のすべてを語ることができるわけではありません。

横浜・みなとみらいエリア
横浜はそれぞれの地域の成り立ちや地形、社会・環境・産業資源の性格などから、「臨海都心部」と「既成市街地(インナーシティエリア)」、「郊外部」の三層でその都市構造を捉えるべきだと考えています。
ちなみに加藤さんが育ったのは保土ヶ谷区星川ですよね。星川は帷子川の下流域にあり、江戸後期に新田として埋め立てられたデルタ地帯に接する、典型的なインナーシティエリアの街です。
横浜開港によって、横浜港に流れ込む河川流域のデルタ地帯に運河が創られ、大正から昭和の初めにかけてこの運河沿いに横浜港とつながる工場地帯が形成されました。だから星川にも昔はビール工場や紡績工場など大きな工場が沢山ありました。加藤さんが生まれた頃には既にマンションとかに変わってしまっていたかも知れませんが(笑)。
ところで、横浜市内を流れる河川は源流から河口までどれもコンパクトで、短いですよね。だから下流から河口域になっても十分な平地を形成することができず、すぐに崖地になってしまいます。
それゆえに港ができて、運河がつくられ、その周辺に工場地帯が形成されたら、市民は崖の上に住まわざるを得ません。横浜のインナーシティエリアは、中区の山手などが典型ですが、小高い崖の上にびっしりと住宅地が張り付いています。昭和の初めの頃から工場地帯に隣接する桜ヶ丘などの崖地に住宅地が形成されたのです。
高級住宅街として知られる横浜市中区・山手。その名の通り、山の斜面に家が立ち並ぶ。
こうした東部圏域の市街地形成に大きな役割を果たしたのが「市電」(路面電車)の存在です。伊勢佐木町を筆頭に弘明寺や大口、六角橋、洪福寺など市電の主要なターミナルには、商店街が形成され、臨海部や運河沿いの崖線に位置する住宅地が市電によって網の目のように結ばれていきました。
このように市電を動線にして崖線と運河と港が結ばれることで市街地が拡大するという構造は、第二次世界大戦や戦後の復興を経て基本的には昭和30年代まで続き、今でもインナーシティエリアを形づくる街の骨格として残されています。
一方で内陸郊外部の市街地は、1960年代以降に東京や横浜のインナーシティエリアからのマイホームを求める大量の流入人口を受け入れることで形成されました。1960年代は、日本列島において稀に見る「民族大移動」が起こった時代です。戦後のベビーブームによって生まれた世代(団塊の世代)が青年期を迎えたこともあり、東北の農村を中心に全国各地から集団就職などで膨大な数の若年労働者が職を求めて東京や横浜、川崎のインナーシティエリア(京浜工業地帯等)に押し寄せました。
若者たちは、最初は工場や会社の寮、商店などに住み込みで働きますが、結婚して子どもができたりすると自分の家が欲しくなります。ところが、当時の東京都内や横浜のインナーシティエリアは人口過密状態で、大気汚染や水質汚濁もひどく、居住環境は最悪でした。
横浜の湾岸沿いにある京浜工業地帯。かつて大気汚染なども深刻だった。
そこで、不動産事業者や宅地開発事業者がこうした若年世帯の旺盛な住宅需要に目をつけ、京浜工業地帯に近接する横浜の内陸丘陵部に大規模な住宅開発を行いました。それまでこのエリアの土地利用は大半が農地山林で、住民のほとんどが農家でした。そのため、主食は自分の田畑でとれた米や野菜、生活用水は井戸水で、食事の煮炊きや風呂を沸かしたりするのは近くの雑木林の薪を活用した自然エネルギー、排泄物や生ゴミは畑の堆肥にといった、自給自足の循環型の暮らしをしていました。そんな農村にいきなり、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活になじみ始めた若い都市住民の住宅がどんどんと建つわけです。これはどう考えても社会問題になりますよね。
例えば、その当時、内陸郊外部にある戸塚区汲沢に東京から引っ越してきた27歳の主婦が、こんな訴えの手紙を横浜市長に書いています。
「私は一昨年十月に結婚しまして、この戸塚区に住むことになりました。東京から横浜へ移る時は、横浜市ということで、港のあるヨコハマに住めるのだと、今考えると大変ロマンチックに考えておりました。ところがこの戸塚区に住んでみますと、港どころか大変な田舎にきたものだとがっかりしています。この汲沢方面は道らしい道が一つもございません。雨が二、三日降れば長靴で半分くらいは土の中に入ってしまうのです。それを三十分もかかってバス停留所まで行かなければなりません。苦情は、道路だけではありません。ガケ崩れの危険、ごみの回収、水道のことなど、毎日の生活がいやになるくらいあります。あこがれの港にも、昨年からたった一回行っただけです。」(横浜市民生活白書39・1964年発行より)
横浜の郊外における市民生活が、こういう場所から始まったという事は記憶に留めておいても良いと思います。
それにしても、1960年代の横浜は、内陸郊外部だけでも毎年人口が7~8万人増えていた時代。急増する人口と虫食い的な市街地開発に対して、上下水道や生活道路、保育園、学校、バス等の公共交通などの基本的な生活インフラの整備が追いつかず、この「市長への手紙」のように市政に対する郊外部住民の要望が噴出した時代でした。
もっともこのような持続可能性の低い乱開発は、1969年の都市計画法の新たな制度によって市街化調整区域と市街化区域の線引きが実施されたり、宅地開発指導要綱等が施行されるなど、開発行為や建築行為のコントロールが行われることによって鎮静化していきます。
そして1970年代の中頃から90年代にかけて、田園都市線や根岸線、市営地下鉄3号線、相鉄いずみ野線など鉄道路線の新規整備延長と住宅開発が一体的に進められていきます。この時代の宅地開発の特徴は、区画整理などの手法を活用することで計画的に、そして丘陵の地形そのものの改変をともなうほど大規模に展開されたことです。

横浜市の住宅街エリア
美しい街並みや緑豊かな自然環境といった住環境における「うるおい・アメニティ」の要素と、住宅から駅が近く、駅周辺に商業施設が集積しているという「生活利便性」の要素とが両立する「第4山の手」と呼ばれ、首都圏の高学歴・高所得のホワイトカラー層の住宅地として人気を博しました。
また、横浜の内陸郊外部は農業専用地区の指定など都市計画上の工夫により、住宅地に隣接する形で農地がかなりの面積で残されていることも特徴です。横浜が現在でも都市農業が盛んなのはこのためで、このことは、今後、横浜においてサーキュラーエコノミーの展開を考えていくうえで重要なフックだと思っています。
このように19世紀後半から20世紀後半にかけて形成された横浜の市街地ですが、21世紀の現時点で、自然地形や道路鉄道網、人口バランスや産業資源の集積などで、市域に都市圏を設定すると、この地図のように東西南北と4つの圏域を設定することができます。
![]()
「臨海都心部」と「インナーシティエリア」で「東部圏域」を構成し、「内陸郊外部」は南部、西部、北部の3つの圏域に分けることができる。各々の圏域で80万~110万の人口を抱えているので、それぞれが政令指定都市として独立できるだけの規模感を持っています。
また、特徴的なのはこれらの東西南北の圏域はそれぞれが完結した生活圏になっていて、人々が日常生活の中で各圏域間を移動することがあまりないという点です。特に北部の住民は、職場も休日遊びに行くのも東京という方が多いですね。
横浜のシビックプライドが高い理由
関口氏:続いて横浜の市民気質についてですが、一言で言うと、横浜市民は「3日住めばハマっこ」とも言われるように、非常に開放的です。元をただせばみんな他の地域から移り住んできたよそ者だからです。
横浜以外の日本の大都市、例えば大阪や福岡、名古屋、仙台は、中世から近世にかけて武士たちが創った城下町です。一方で横浜の臨海都心部は、港を中心にして、商人たちが創りあげた、現代的に言えばアントレプレナー(起業家)たちによって築かれた町です。若くて野心的で、これまでにないような新しい事業を興したい、港・横浜で一旗挙げようという横浜商人たちによって港・横浜は築かれました。私の生まれ育ったところは、西区平沼で、私は3代続いたハマっ子です。祖父母からそういう横浜の歴史について聞かされて育っているので、横浜という街への愛や特別な感情、責任、プライドを持っています。私に限らず、横浜の東部圏域で生まれ育った人は、そういう人が多いと思います。
横浜市中心部の風景。
一方で、1960年代~70年代にかけて東京から横浜の内陸郊外部に移り住んできた人たちは、先ほど述べたように、それまで農地山林だったところに家だけが建てられて、生活インフラも住民同士のつながりもが全くない状態で、自治会・町内会などの地縁組織を結成し、自分たちの手で保育園や学童保育を開設、運営したり、行政や開発事業者と交渉しながら学校や公園、商業施設などを整えてきました。そのため、この街は自分たちが創ったまちだという意識が非常に強いわけです。
また、1980年代以降に横浜の内陸郊外部に転入してきた市民も、美しい街並みや緑豊かな自然環境を持ち、そして住宅から駅が近く、駅周辺に商業施設が集積している横浜郊外の計画的につくられた街の環境が気に入って住み続けている人が多い。
だからこそ横浜市民は自らが住む街に愛着を持つ人が多く、市民意識調査などをすると、約8割の市民が横浜に対して愛着や誇りを感じていると答えるわけです。これは都市としての持続可能性を考えるうえでとても大切なことだと思います。
横浜市が抱える課題とは?
関口氏:最後に、横浜市の持続可能性を考える上での課題としては大きく二つ挙げることができます。
一つは、市域全体で高齢化が急速に進んでいることです。2020年1月1日現在で、横浜市内の65歳以上の高齢者の人口割合は24.7%。この20年間で10ポイント以上も上昇し、2025年には65歳以上の高齢者だけで人口が約100万人になると予測されています。
さらに地域ごとに高齢化の偏差が大きく、例えばインナーシティエリアの崖地の住宅地や内陸郊外部のバス圏にある住宅団地では高齢化率が40%から50%に達する地域もあり、人口減少による空き家も目立つようになっています。
特にこのような超高齢化が世帯の単身化とセットで進んでいることが大きな問題で、認知症に対するケアや買い物難民の問題など課題は山積みなのですが、このコロナ禍によって単身高齢者がますます自宅に引きこもるようになっているという話を様々な場所で聞くようになり、単身高齢者の孤立化が深まらないか、とても心配です。
横浜の課題を考える上でのもう一つのポイントは、「東京」に近接しているという点です。例えば、横浜の昼夜間人口比率は、91.7と100を割っています。つまり昼間に他都市から横浜に働きに来ている人よりも、横浜から他都市に働きに行っている人の方が多いということです。
これは、世界的に見ても375万の人口を抱える大都市では余り例のないことです。例えば大阪も名古屋も福岡も仙台も札幌も、昼夜間人口比率は100を越えています。なぜなら政令指定都市クラスの大都市には民間企業や公共セクターなどが集積することで、各地方圏の政治・経済センター的な役割を果たしており、周辺の都市から労働人口を引き寄せるからです。
ところが、横浜の場合は逆に労働人口を市外に持って行かれてしまう。それは東京という世界的な大都市が横浜に近接しているからです。
平成元年の横浜市行政区別人口増加率
20世紀後半の横浜市は、東京から大量の流入人口を引き受けることで、いわばベッドタウンとしての住機能に特化したまちづくりを行ってきました。市民の環境を守るため、公害を撒き散らす企業はなるべく市外に出ていってもらうというスタンスで市政を運営していました。その結果、市内の産業集積が薄くなり、市内経済が活性化しなくても仕方がないという考え方でした。
それは、北部圏域で典型的に見られるように世帯主である男性が東京に稼ぎに行き、女性は地域に残り、家事や子育てや介護に専念する、という当時の市民のマジョリティだった核家族のあり方やその価値観、ニーズと適合していたわけです。
ところが21世紀に入ると共働き世帯や単身世帯が増えることで、交通が不便で通勤に時間がかかる郊外の住宅地を若年世代が選択しなくなってきました。すなわち人口の都心回帰現象が顕著になり、労働人口だけではなく30歳代~40歳代の働き盛りの市民の居住人口まで東京に奪われるようになったのです。
このことが市域の少子高齢化に拍車をかけています。さらに人口の割には産業集積が薄く、税収は個人市民税に依存する構造になっています。従って、このまま有効な手を打たなければ、横浜市の財政予測として、社会保障費は膨らんでいくものの逆に税収は細っていくという悪循環に陥っていきます。これは横浜市として、本当に危機的な状況です。
だからこそ、この危機を乗り越えるためには、20世紀後半の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムからいち早く抜け出し、日本のどの年寄りも先に循環型経済へと転換していく必要があるわけです。
編集後記
「横浜に住んでいる人は、自身のことを神奈川県民ではなく横浜市民と定義する」こんな笑い話を聞いたことはないでしょうか。
それは、ただ単に横浜市民が横浜という土地に高いプライドを持っているからという理由ではないことが、今回の対談で垣間見えたように感じます。市外からやってきた商人たちによって形作られ、現在では人口375万人、各々の圏域には80万~110万の人々が暮らす街。このような独自性を持った大都市は、周りを見渡しても横浜しかないのです。
それでは、これからの横浜が地球の持続性を保ちながらより住みやすい街として発展していくためには何が必要なのでしょうか。対談の中編では、横浜がサーキュラーエコノミーを推進していくべき理由や、横浜ならではの強みについて詳しく掘り下げていきます。